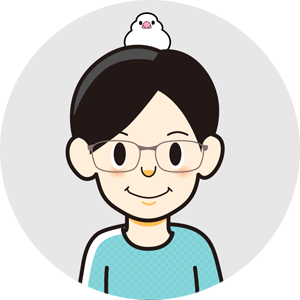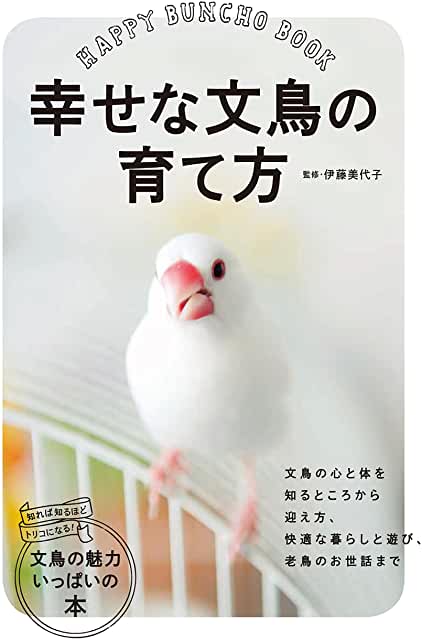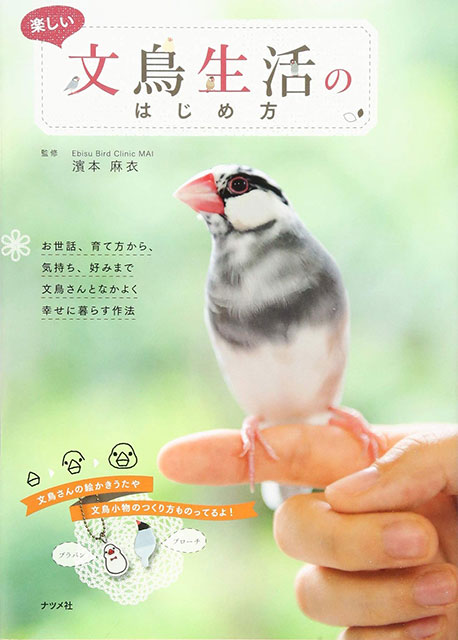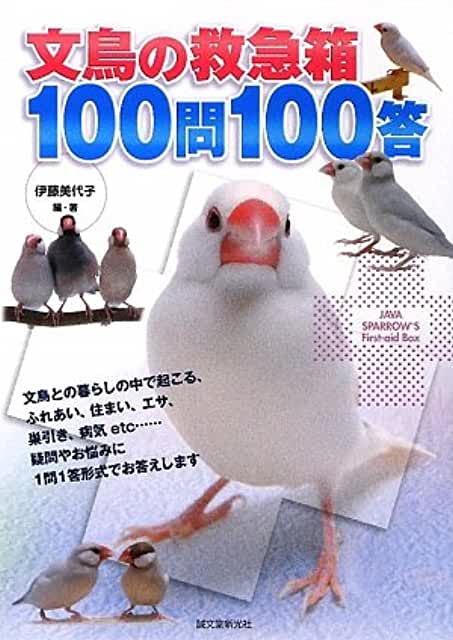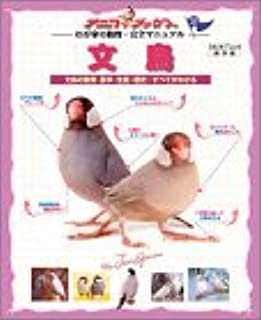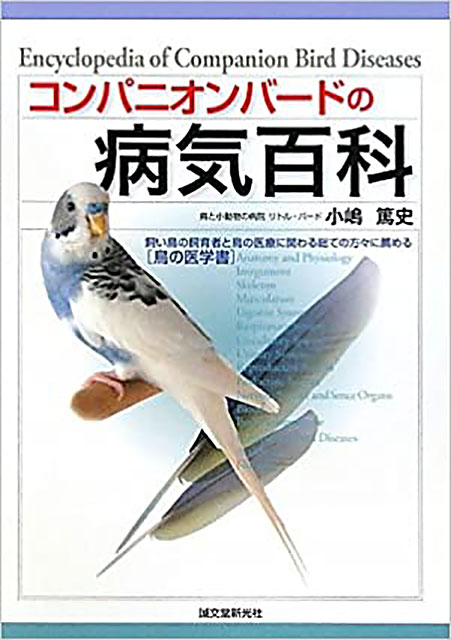文鳥のヒナの育て方
公開日 最終更新日 | 飼育方法

文鳥のヒナはとても弱く、温度・湿度管理ができていなかったり、ご飯から十分な栄養が補給できないと、死んでしまうことも珍しくありません。
ヒナを守るための環境と、成長過程に応じた育て方をご紹介します。
温度・湿度管理
まずはヒナにとって最適な温度と湿度を維持してあげなければいけません。温度・湿度の管理を怠ると、ヒナの死に直結してしまうからです。
成長過程ごとの適温・適湿については、次の数値を参考にしてみてください。
※暑いときは開口呼吸をしたり、呼吸が速くなります。寒いときは羽を膨らませたり、片脚をお腹の羽の中に入れて熱を逃さないようにします。以下は参考値なので、文鳥の様子をみながら温度を調整してあげてください。
病気のときにも、口を開けたり、羽を膨らませることがあるので、温度が原因でないと感じたら病院で診てもらいましょう。
| 生後1~21日 | 温度:30~32度 湿度:80% |
|---|---|
| 生後22~28日 | 温度:28~30度 湿度:70% |
| 生後29~63日 | 温度:25~28度(換羽期の場合は26〜30度) 湿度:60% |
用意するもの
成鳥用のケージでは温度や湿度を一定に保つことが難しいので、次のものを用意します。
【必要なもの】
- ・プラスチックケース(大きめのもの)
- ・ふご(生後3週間はふごの中で育てる)
- ・ヒーター(保温するための器具)
- ・サーモスタット(温度を自動調整する器具)
- ・温度・湿度計
- ・濡れタオル(保湿用)
- ・仕切り(ヒナの居住スペースと濡れタオルを仕切るため)
- ・濡れタオルを入れる容器(仕切りがない場合)
- ・ティッシュペーパー※(底に敷き、クッションになるよう、その上からくしゃくしゃにして4~5枚入れる)
- ・バスタオルや毛布など大きめの布(保温 + 就寝時に暗くするため)
- ・あわの穂(生後4週目くらいからひとり餌の練習をする)
- ・止まり木(生後4週目くらいから木に止まるようになる)
※クッション材として、おがくずを敷くと、飲み込んでしまったり、目を傷つける危険があります。
※骨格ができあがり、脚の力で自分をしっかり支えることができるようになったら、キッチンペーパーを平らに敷いても良い。
成鳥過程ごとのお世話
| 生後1~14日 | 親鳥に育児を任せます 育児放棄をした場合は、人間が挿餌を1時間おき(1日10~13回)に与える |
|---|---|
| 生後15~21日 | ふごの中で育てる ご飯のとき以外はふごから出さない(フタをしておく) 挿餌を2時間おき(1日6~7回)に与える |
生後22~28日 | プラスチックケースで育てる 普段は毛布で覆って保温し、1日1時間くらい明るい時間を過ごす 挿餌を2~3時間起き(1日5~6回)に与える ひとり餌の練習用にあわの穂を入れておく |
| 生後29~35日 | プラスチックケースで育てる 明るい時間帯に少しづつ成鳥用のケージに慣らす(ケージはしっかり保温しておく) 挿餌を2~3時間起き(1日5~6回)に与える ひとり餌の練習用にあわの穂と成鳥用のご飯(ペレットやシード)を入れておく 少しずつ放鳥に慣らしていく 水浴びや日光浴を始める ※この頃から文鳥は、いろんなことを覚える学習期(生後84日くらいまで)に入ります。いろんなことに興味を持って噛みつくこともありますが、おおらかに見守りましょう。警戒心の少ない学習期に優しく接することで、文鳥は自然と人間を信頼するようになります。 ※この時点で体重が20g以下の場合は、病気の可能性があるため医師に診てもらいましょう。 |
| 生後36~42日 | 成鳥用のケージに引っ越す(ケージはしっかり保温する) 成鳥用のご飯(ペレットやシード)を用意する(成鳥用のご飯をちゃんと食べているか、減っているかを確認する) 挿餌を欲しがるなら1日1~3回与える |
| 生後43~63日 | 成鳥用のケージで過ごす(ケージはしっかり保温する) 成鳥用のご飯(ペレットやシード)を用意する ひとり餌を覚えない場合は、ご飯をばらまいて指先で注意を引くようにトントンとつついて、食べるように促す。 挿餌を欲しがるなら1日1~3回与える ※この頃から成鳥の羽に生え変わる換羽が始まります。羽が抜け、生え変わるために体力を奪われ、怒りっぽくなります。換羽が終わるまでは、ケージ内の温度を26~30度くらいにして、しっかり保温してあげましょう。 |
| 生後64~84日 | 成鳥用のケージで過ごす(換羽期が終われば、ケージ内の温度は成鳥の適温20~25度でよい) 成鳥用のご飯(ペレットやシード)を用意する |
まとめ
仕事などで家を空ける時間が多く、数時間おきに挿餌ができない場合は、ひとり餌を覚えた生後5週齢くらいのヒナをお迎えするのがおすすめです。
飼い主が挿餌をしなくても、学習期(生後29~84日くらい)に優しく接することで、よく馴れた手乗り文鳥にすることは十分に可能です。
無理してお迎えしようとせずに、文鳥も飼い主もお互いに準備が整ってから、家族として迎え入れましょう。